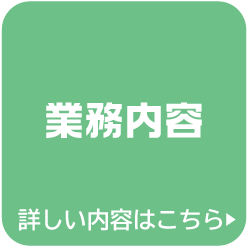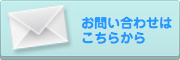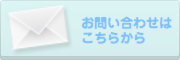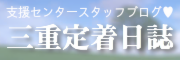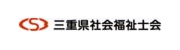お知らせ
ホームページを更新しました。
2023年12月28日
パンフレットを新たに発行しました。右のボタンからご覧いただけます。
2023年12月12日
広報紙「つながり」16号を発行しました。右のボタンからご覧いただけます。
2023年10月25日
令和5年度第1回特別調整に係る関係機関等連絡会に参加しました。
令和5年7月11日、津保護観察所にて連絡会が開催され、職員4名が参加しました。現在、矯正施設に入所・入院中の人、退所・退院した人たちのことについて、津保護観察所、三重刑務所、宮川医療少年院、三重県地域生活定着支援センター、三重県保護会、三重県子ども・福祉部地域福祉課のメンバーで情報共有と課題などを話し合いました。コロナ禍で中止になったこともありましたが、今年度は3回実施していく予定です。
2023年7月11日
広報紙「つながり」15号を発行しました。右のボタンからご覧いただけます。
2023年2月20日
↓ダウンロードしてご覧頂けます↓
 センター パンフレット
センター パンフレット
※定着支援センターのパンフレット
 Aさんの定着ものがたり
Aさんの定着ものがたり
※定着支援センターの説明
 つながり・・・第16号
つながり・・・第16号
 つながり・・・・第15号
つながり・・・・第15号
 つながり・・・・第14号
つながり・・・・第14号
 つながり・・・・第13号
つながり・・・・第13号
 つながり・・・・第12号
つながり・・・・第12号
 つながり・・・・第11号
つながり・・・・第11号
 つながり・・・・第10号
つながり・・・・第10号
 つながり・・・・第9号
つながり・・・・第9号
 つながり・・・・第8号
つながり・・・・第8号
 つながり・・・・第7号
つながり・・・・第7号
 つながり・・・・第6号
つながり・・・・第6号
 つながり・・・・第5号
つながり・・・・第5号
 つながり・・・・第4号
つながり・・・・第4号
 つながり・・・・第3号
つながり・・・・第3号
 つながり・・・・第2号
つながり・・・・第2号
 つながり・・・・創刊号
つながり・・・・創刊号
※定着支援センターだより